劣等感とどう向き合う?アドラー心理学から学ぶ「自分を変えるヒント」
「どうして私ばかり…」「私なんて何をやってもダメ」
こんなふうに、自分を責めたり、人と比べて落ち込んだりした経験はありませんか?
実はその背景には、「劣等感」という人間なら誰しもが持つ感情があります。
この言葉は、ベストセラー『嫌われる勇気』で有名になったアドラー心理学の中核をなす概念。
ただし、劣等感自体は悪いものではなく、むしろ成長のための大切なサインでもあるんです。
私自身も劣等感に押しつぶされそうになった時期がありました。
「人と比べて自分は劣っている」「どうせ私なんて」と落ち込むこともあれば、逆に「私はこんなに頑張っているのに!」と怒りをぶつけてしまうこともありました。
きっと、この記事を読んでいるあなたも同じように、日常の中で劣等感に悩む瞬間があるのではないでしょうか。
そこで今回は、アドラー心理学の中核をなす考え方である 「劣等感」と「劣等コンプレックス」の違い について解説していきます。
この違いを理解することで、自分を責め続ける日々から抜け出し、より健全に劣等感を生かすヒントが見えてきますよ。
劣等感と劣等コンプレックスの違い
ここで改めて、「劣等感」と「劣等コンプレックス」の違いを整理してみましょう。
🌱 劣等感とは?
劣等感とは、「私にはまだ足りないところがある」「もっと成長できる余地がある」という気づきです。
つまり、劣等感は本来、前に進むためのエネルギー源なんです。
たとえば…
- 職場で後輩が活躍していて「私ももっと頑張ろう」と思えた時
- 友人が資格を取って刺激を受け、自分も学び直そうと感じた時
こうした気持ちは一見つらいですが、「成長のサイン」でもあります。
🌀 劣等コンプレックスとは?
一方、劣等コンプレックスは、この「足りない」という感覚を健全に受け止められず、言い訳や正当化、逃避に変えてしまった状態です。
具体的にはこんな形で表れます:
- 「どうせ私なんて…」と挑戦すらしなくなる
- 「あの人が悪い」と周りのせいにして動かない
- 必要以上に人を見下し、自分を守ろうとする
つまり、劣等感を成長に使うか、それとも自分を縛る鎖にするかで未来が大きく変わってしまうんです。
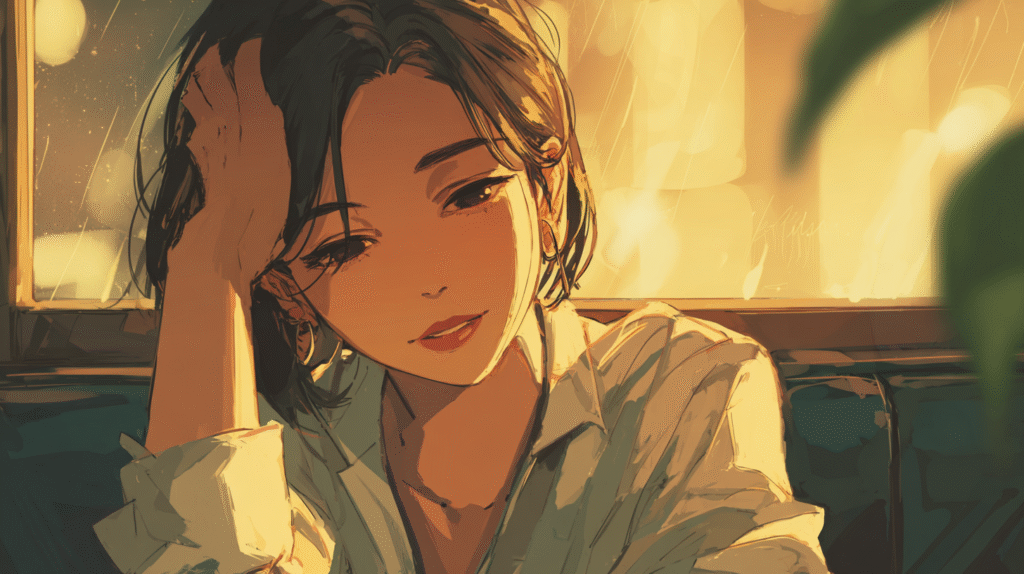
🔑 ポイント
- 劣等感=自然で健全な感情(誰にでもある)
- 劣等コンプレックス=劣等感をねじ曲げ、言い訳や行動停止に変えてしまったもの
アドラー心理学では、劣等感そのものをなくそうとするのではなく、どう向き合い、どう生かすかが大切だとされています。
劣等感に振り回される私たち
多くの人は「他人の評価」によって一喜一憂しがちです。
- SNSの「いいね」の数で、自分の存在価値を測ってしまう
- 職場での上司や同僚のちょっとした言葉に、必要以上に落ち込んでしまう
- 友達の結婚や出世と比べて、「自分の人生って情けないな」とため息をついてしまう
こうした背景には、「私は認められたい」「必要とされたい」という強い欲求があります。
これは人間にとってごく自然な気持ちであり、昨日の記事で触れた「課題の分離」や「承認欲求」とも深くつながっています。
劣等感は本来、成長のサイン
劣等感そのものは「足りない部分を教えてくれるセンサー」であり、本来は成長のエネルギーになるものです。
「もっと学びたい」「もっと力をつけたい」という前向きな気持ちは、劣等感があってこそ芽生えます。
劣等感がねじれると…
しかし、この感情に振り回されすぎると「劣等コンプレックス」に変わってしまいます。
- 「どうせ私なんて…」と挑戦すら避ける
- 「あの人ばかり評価されて不公平」と他人のせいにして動けない
- 「私はすごいんだから!」と過度に攻撃的・批判的になってしまう
つまり、劣等感をエネルギーに変えられるか、それとも自分を縛る鎖にしてしまうかで、その後の人生が大きく変わるんです。
アドラー心理学が教えてくれるのは、劣等感を「敵にしない」こと。
むしろ自分を成長させるためのヒントとして活かせるようになることです。
劣等感を健全に生かす人・コンプレックスに囚われる人
ここでいくつか具体例を見てみましょう。
- 恋愛の失敗
劣等コンプレックス化:過去のトラウマから「もう誰も私を愛してくれない」と諦めてしまう。
健全な活用:経験を振り返り「次はこうしてみよう」と自己成長に結びつける。 - お金や家庭環境
劣等コンプレックス化:「どうせ貧乏だから努力しても意味がない」と行動をやめてしまう。
健全な活用:「過去に不便を経験したからこそ、今は自分の力で未来を変えよう」と努力を続ける。 - 人間関係
劣等コンプレックス化:「嫌われるくらいなら最初から関わらない」と孤立する。
健全な活用:「怖さはあるけれど、一歩踏み出せば新しい関係が築けるかも」と小さな挑戦を重ねる。
このように同じ出来事でも、「どう解釈して行動するか」で未来はまったく変わるのです。

私自身も「コンプレックスの宝庫」だった
私がこうして劣等感について語れるのは、特別な知識があるからではありません。
読んでくださっているあなたと同じ40代女性として、同じように悩み、苦しみ、劣等感やコンプレックスに振り回されてきた経験があるからです。
実際に私自身も、恋愛・お金・人間関係など、数えきれないほどのコンプレックスを抱えていました。
「もうダメだ」「私なんて」と思ったことも何度もあります。
でも、考え方を少しずつ修正し、できる範囲で行動に変えていくことで、少しずつ現実も変わってきました。
だからこそ、私は心から伝えたいんです。
――大丈夫。あなたも必ず変われる、と。

次のステップ:「勇気づけ」
劣等感を健全に生かすために必要なのが「勇気」です。
アドラー心理学では、人が行動を変える原動力は「勇気づけ」にあるとされています。
次回の記事では、この「勇気づけ」について、具体的な方法や日常での実践ヒントを解説していきます。
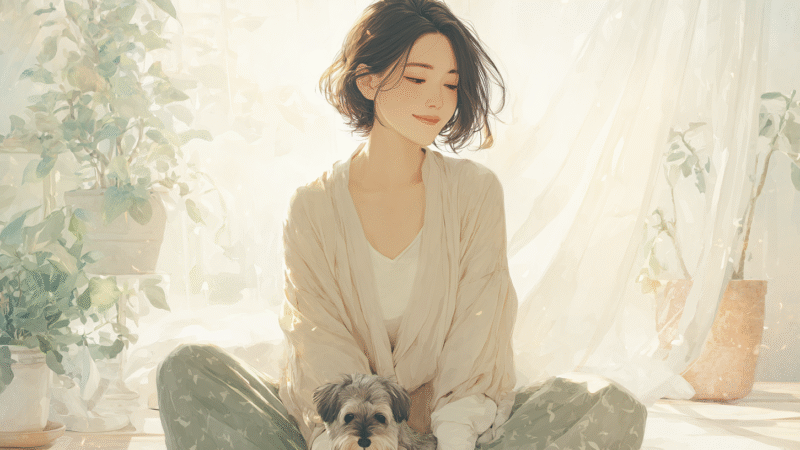
まとめ
- 劣等感は誰にでもある自然な感情。問題はそれをどう扱うか。
- 劣等コンプレックスに陥ると行動が止まり、人生が停滞する。
- 健全な劣等感は、成長と変化の大きなエネルギーになる。
- 行動に変えるためには「勇気」が必要。
👉 あなたの「劣等感」は、まだコンプレックスに変わる前かもしれません。
今こそ、自分を責めるのをやめて、少しずつでも前に進むきっかけにしていきましょう。




